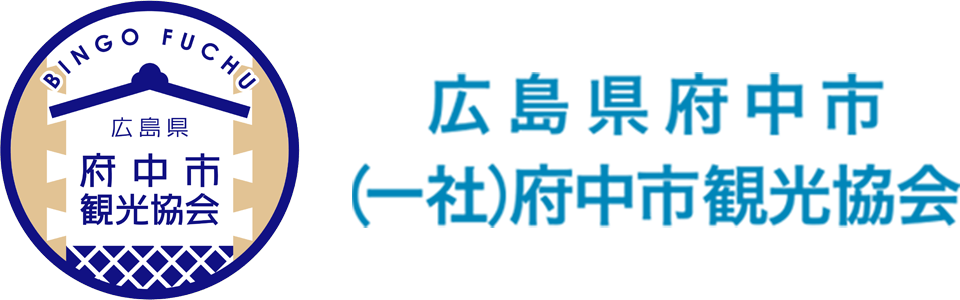歴史・文化|府中エリア
府中八幡神社 ふちゅうはちまんじんじゃ
家具建築の神、鉄鋼の祖神などが祀られる、最古級の本殿形式

府中八幡神社は、八尾城の守護神であったと伝えられますが、荒廃していたため、地元民が現在地へ社殿を再興しました。21年をかけて募金を集め、元禄5年(1692年)に新社殿を造営しましたが、その後さらに壮麗な本殿を新築したため、元禄再建の旧殿は天満宮本殿に転用されて現存しています。この地方によく見られる本殿形式ですが、最古級のものです。保存状態がよく、建立当時の部材がよく残っています。




八幡神社看板より
府中八幡神社は大昔、現社殿の裏山にある「宮の壇」(天狗松ともいう)といわれる場所に八尾城の守護神として祀られました。創立は芦品郡志によれば嘉吉3年(1443年)山名持豊の目代宮田備後守政輝が八尾城に赴任して建立しました。天文7年(1538年)八尾城主杉原理興が神辺城に移ったため、神社は一時さびれたが承応2年(1653年)郷民相計り社殿をこの羽中山に移しました。寛文12年(1672年)府中市の庄屋河面市右衛門直賢が願主となり、元禄5年現在の末社天満宮の社殿を八幡神社の本殿としましたが寛保2年(1742年)更に新な本殿を造営、昭和36年(1961年)消失、昭和44年現在の社殿が再建されました。末社には天満宮をはじめ府中の産業である家具建築の神、鉄工の祖神などが祀られています。

【Recommended course】
この情報が関連したおすすめコースはこちら
【Profile】
| 名称 | 府中八幡神社 |
|---|---|
| 所在地 | 広島県府中市出口町162 |
| 問合先 | 電話:0847-41-2304 |
| 関連イベント | 府中八幡紅葉まつり |
【Access】
関連リンク